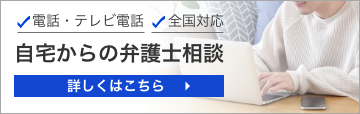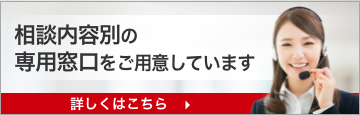「残業するな」は問題ない? 違法性やリスク、対処法を弁護士が解説
- 労働問題
- 残業するな

残業削減に向けた取り組みとして、“ノー残業デー”や“残業の事前申請”などを行う企業が増えています。
しかし、業務量が変わらないのに「残業をするな」と圧力をかけるのは、いわゆる時短ハラスメントと評価される可能性があります。時短ハラスメントは従業員から訴えられるリスクもあるため、適切な対策を講じることが重要です。
今回は、残業禁止命令が招くリスクとその対処法について、ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスの弁護士が解説します。
1、「残業するな」と伝えても問題ない?
従業員に対して「残業するな」と伝えることは、状況によっては、時短ハラスメントにあたる可能性があります。以下では、時短ハラスメントの概要とその具体例を説明します。
-
(1)時短ハラスメント(ジタハラ)とは何か
時短ハラスメントは、法律上の定義があるわけではありません。一般には、企業が必要な対策を講じることなく、労働時間の短縮を強要するハラスメントを指す言葉です。時短ハラスメントを略して「ジタハラ」と呼ぶこともあります。
近年、長時間残業が深刻な社会問題となっており、各企業では、残業時間を減らすためのさまざまな取り組みが行われています。残業時間を短縮することは、労働者の負担軽減にもつながりますが、業務量が変わらないにもかかわらず、残業時間だけを減らしても根本的な解決にはなりません。
労働時間の短縮を強要された労働者は、定時までに処理しきれなった仕事を自宅に持ち帰ったり、休日に行ったりするなど、実質的にはサービス残業を強要しているのと同様の状態といえるでしょう。
そして、そのように結局のところ計測されない時間外残業を生むと、残業代の問題だけでなく、労働時間に関連した不法行為やパワハラに該当する可能性があるので、企業としては十分に気を付けて対応しなければなりません。 -
(2)時短ハラスメントの具体例
時短ハラスメントにあたる具体的な行為としては、以下のようなものが挙げられます。
- 現場の状況を把握せずに、一方的に「残業をするな」と命令する
- 残業しなければ処理できない業務量にもかかわらず「残業をするな」と命令する
- 業務時間を短縮する具体的な対策をせず“ノー残業デー”や“強制消灯”を実施する
- 自宅に仕事を持ち帰っていることを知りながら何も対策を講じない
2、「残業するな」が招くリスクとは?
適切な対策を講じることなく「残業するな」と命じると、以下のようなリスクを招くおそれがあります。
-
(1)仕事を持ち帰ることで情報漏えいの危険性が高まる
「残業するな」と命じられた従業員は、会社で仕事ができなくなりますので、処理しきれなかった仕事を自宅に持ち帰って行わなければならなくなります。
自宅やカフェなどで仕事をすると、重要な書類やデータを紛失してしまうなどの情報漏えいの危険性が高くなります。万が一、個人情報や顧客情報などが含まれたデータが流出してしまうと、企業の情報管理責任が問題となり、多額の賠償金の支払いを命じられるリスクも生じてしまいます。 -
(2)業務効率や品質が低下する
業務量が変わらないにもかかわらず、残業が減らされ、労働時間が少なくなると、短い労働時間の中で業務を終わらせなければなりません。
当然、早く仕事を終わらせるためにも品質を犠牲にせざるを得ませんので、仕事の品質の低下を招き、顧客や取引先からクレームがくる可能性があります。
また、定時に終わらない仕事は持ち帰って対応しなければなりませんが、会社からは「残業するな」といわれているため、残業代を請求することができず、サービス残業となってしまいます。残業代がもらえなくなれば従業員のモチベーションも低下してしまい、業務効率の低下を招くおそれがあります。 -
(3)未払い残業代の問題に発展する可能性がある
「残業するな」と命じていたとしても、実際に残業をしなければ処理できないような業務量であった場合には、残業代の支払いが必要になります。
残業代を支払っていないと、サービス残業を強いられた従業員から未払い残業代の請求をされることになり、そのために多額の費用を負担しなければなりません。
3、時短ハラスメント状態にならないための対処法
時短ハラスメント状態にならないために企業ができる対処法としては、以下のようなものが挙げられます。
-
(1)業務量や人員配置の適正化を図る
時短ハラスメントは、業務量の調整や削減をせずに、残業時間だけを削減することが原因で生じます。そのため、まずは、業務量や人員配置の適正化を図ることが重要です。
特定の部署や従業員に対して業務が偏っているような場合には、他の部署や従業員に適切に割り振るなどして業務負担の平均化をしましょう。また、当該部署の人員が不足しているために残業が発生しているという場合には、新たな労働力の補充も検討する必要があります。 -
(2)従業員の勤務時間を適正に管理する
会社側が把握している労働時間と実際の労働時間に食い違いがあると、労働者に対して過剰な業務負担をかけてしまうこともあります。特に、サービス残業が常態化しているような会社では、労働時間の認識に大きな差が生じていることも珍しくありません。
そのため、会社としては従業員が会社に申告していない部分まで含めた勤務時間を把握することが重要になります。従業員と管理職が個別に面談するなどして、適正な勤務時間の把握に努めるようにしましょう。 -
(3)業務の効率化を図る
残業時間を削減するためには、現状の業務効率を見直して、より生産性の高い方法を導入する必要があります。近年では、業務効率の改善のためにITツールなどを導入する企業も増えてきていますので、こちらも積極的に検討してみるとよいでしょう。
-
(4)社内に相談できる窓口を設置する
時短ハラスメントに限らず、従業員が気軽に労働問題について相談できる窓口を設置することも重要です。相談窓口に寄せられた従業員からの苦情や意見などを踏まえて、労働環境の改善に努めることで、時短ハラスメントのない職場を作り上げることができます。
また、早期に時短ハラスメントの疑いのある事案を把握することができれば、問題が深刻化する前に解決することが可能となります。
4、労務トラブルを弁護士に相談するメリット
労務トラブルについては、以下のようなメリットがありますので、弁護士に相談するのがおすすめです。
-
(1)従業員と代理で交渉してもらえる
従業員との間で労務トラブルが生じた場合、企業の担当者は、当該従業員とのトラブル対応にあたらなければなりません。しかし、労務トラブルの解決には法的知識や経験が不可欠です。知識や経験が乏しいまま対応にあたると、トラブルを深刻化させるリスクがあります。
労務問題の実績がある弁護士にトラブルの対応を任せることで適切な対応が期待できます。また、トラブルに対応する担当者も本来の業務に集中することができますので、貴重なリソースを失うこともありません。 -
(2)会社のルールが法的に問題ないか確認できる
残業時間の削減自体は、好ましい取り組みといえますが、業務量の調整なく「残業するな」と命じるだけでは、根本的な解決にはならず、時短ハラスメントのリスクがあります。
会社がこれから行う取り組みが法的に問題ないかどうかを判断するためには、弁護士に相談するとよいでしょう。弁護士であれば、法的観点から会社のルールの問題点などを指摘し、改善に向けたアドバイスができます。弁護士のアドバイスに従って対応することで、労務トラブルを回避することができるでしょう。 -
(3)労働審判や裁判の対応を任せられる
労務トラブルが労働者との話し合いで解決しない場合、労働者から労働審判の申立てや訴訟提起などをされることがあります。このような法的対応に関しては、知識や経験がなければ対応は困難ですので、弁護士に対応を任せるのが安心です。
5、まとめ
従業員に対して「残業するな」と指示すると、具体的な状況によっては、時短ハラスメントだと捉えられてしまう可能性があります。また、「残業するな」と指示すると、会社で残業をしなかったとしても家に持ち帰って仕事をしたり、未払い残業代の問題に発展したりする可能性もあります。
このように残業禁止命令には、さまざまなリスクが潜んでいますので、法的リスクをクリアしていくためにも、まずは労務問題の解決実績がある弁護士に相談することをおすすめします。従業員との労務トラブルに関するお悩みは、ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスにお任せください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています