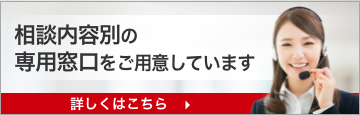従業員が業務命令に従わないときの対処方法|懲戒処分と懲戒解雇
- 労働問題
- 業務命令
- 従わない

「上司の指導や会社からの業務命令に従わない従業員がいる。何度言っても直らないから、懲戒解雇することはできないか?」このような悩みを抱える人事や経営者は珍しくありません。
業務命令に従わないことを理由に懲戒解雇ができる場合もあります。しかし、懲戒解雇は最も重大な懲戒処分であり、法律により厳しく制限されているため、懲戒解雇ができるかどうかは慎重に検討する必要があります。
そこで、この記事では、業務命令に従わない従業員への懲戒処分の方法・注意点などについてベリーベスト法律事務所 姫路オフィスの弁護士が解説いたします。
1、従業員が業務命令に従わないのは、許されることなのか?
会社は従業員に対して業務命令を行うことが可能です。しかし従業員がこれを拒絶し、トラブルとなるケースが多くあります。従業員が業務命令に従わないことは、法律上どうとらえるべきなのでしょうか。
-
(1)そもそも業務命令とは?
法律上、「業務命令はこういったものだ」と業務命令をはっきりと定義した条文はありません。
会社は労働契約を締結した従業員に対して、契約の効力として「監督権限」と「管理権限」を有しています。この監督権限に、従業員に労働条件に従って労働させるための命令権が含まれており、業務の遂行全般について、労働者に指示命令する権限(時間外労働命令、休日労働命令、健康診断受診命令など)があります。
なお、管理権限とは、要するに人事権のことを指し、配置、降格、休職、異動などの人事管理を行う権限をいいます。
このように、会社が労働契約を締結した従業員に対して有している監督権限と管理権限から、会社は業務命令を行い、従業員を従わせることができるのです。 -
(2)従業員の義務|誠実労働義務
一方で、従業員は、労働契約の範囲内で、使用者の指揮命令に従って誠実に労働する義務、すなわち誠実労働義務を負います。誠実労働義務には以下のような特徴があります。
第1に、会社の業務命令・指揮命令に従って労働する義務を負います。
ちょうど、会社が監督権限・管理権限を持つことに対応する関係となります。
第2に、従業員は、単に機械的に、自己の労働力を会社に提供すれば足りるのではなく、会社側の利益を不当に侵害しないよう配慮して行動することも求められます。
労働者が重大な過失によって使用者に損害を与えた場合は債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことがありますが(会社の設備や機械を壊した場合など)、これは、このような配慮が求められるためです。 -
(3)従業員が業務命令を拒絶できるケース
前述のように、企業は従業員に対して監督権限および管理権限に基づいて業務命令権がある一方で、従業員は、誠実労働義務を負うことからこれら業務命令に従わなければならないという関係に立ちます。
しかし、企業の業務命令権もまったくの無制約に認められるわけではありません。従業員は、
① 法令による規制に抵触する場合
② 労働契約上の制限を超えている場合
など、正当な理由があれば業務命令を拒絶することができます。
- ① 法令に抵触する場合
労働基準法・労働安全衛生法などの強行規定や雇用機会均等法6条など各種の差別禁止規定などは、労働契約の内容よりも優先されるため、これらに反する業務命令は拒絶が可能です。 - ② 労働契約上の制限
また、従業員の負担する労働義務と会社が有する業務命令権は、あくまで労働契約の予定する範囲内に限定されます。したがって従業員は労働契約の範囲を超える命令に従う必要はありません。
さらに、労働義務が客観的には労働契約の範囲内にある場合であったとしても、業務命令は労働契約法3条5項による権利濫用の規制の対象になります。
たとえば、公序良俗に反するような命令や嫌がらせ目的の命令のように、業務上の必要性が高くないのに、従業員に過大な精神的・身体的苦痛を与える命令など、労働者の人格的利益(精神・身体の自由、名誉、プライバシー)を不当に侵害する命令が典型であり、そのような業務命令は権利の濫用として無効になるとともに、民法上の不法行為に該当してしまう場合には会社が従業員から損害賠償を請求される可能性すらあるので、注意が必要です。 - ① 法令に抵触する場合
2、業務命令に従わない従業員に対して会社側ができること
上司による注意・指導を繰り返しても改善せず、業務命令に従わない従業員に対しては、以下のように懲戒処分などを検討することになります。
懲戒処分
懲戒処分には、けん責(戒告、訓告)処分、減給処分、出勤停止処分、降格(降職)処分、懲戒解雇処分などがあります。
- けん責(戒告、訓告)処分
従業員に注意を与え今後を戒める処分で、懲戒処分のなかでは最も軽い処分です。一般的に、けん責処分は始末書の提出までを求めるものであることが多く、始末書の提出を求めない場合には戒告処分・訓告処分と呼ばれることが多いです。 - 減給処分
従業員の賃金を減額する処分です。労働基準法では、ひとつの事案における減給額は平均賃金の1日分の半分以下、複数事案における減給の総額は一賃金支払期の賃金総額の10分の1以下のものでなければならないと定め、減額幅について制限を置いています。 - 出勤停止処分
労働契約は存続させつつ、従業員の労働の提供を停止させる処分です。出勤停止期間中は、賃金が支払われない取り扱いがされることが一般的です。 - 降格(降職)処分
従業員を懲戒することを目的に、役職や職能資格を低下させる処分をいいます。 - 懲戒解雇処分
懲戒処分として解雇することであり、懲戒処分のなかで最も重い処分です。懲戒解雇と普通解雇の違いは、制裁としての解雇である点です。懲戒解雇の場合には一定の手続をとることにより解雇予告を伴わないで即時に解雇することが認められるほか、退職金の全部または一部を支給しないなどの規定が置かれていることが一般的です。
3、従業員の懲戒処分・懲戒解雇を判断する前に注意すべきこと
従業員が業務命令に従わないとき、懲戒処分を行うにあたっては注意するべきことがあります。特に懲戒解雇を行う場合には、極めて慎重に対応をする必要があります。
なお、何らかの懲戒処分を行う前に、まずは対象となる従業員に対して、業務命令に従わない経緯や理由などを聞き、改善するための機会を与えましょう。
-
(1)業務命令の有効性
業務命令に従わない従業員に対する懲戒処分を行うにあたっては、まずそもそも有効な業務命令であったのか、という点が重要なポイントになります。
具体的には、
① 業務命令を行う根拠があるか(就業規則などで定められており、それが労働契約の内容になっているのか)
② 業務命令の行使が正当か(濫用になっていないか)
を検討するというステップを踏む必要があります。
②については、命令権行使に業務上の必要性はあるかどうか、行使の目的に不当性はないか、行使がどの程度、従業員に就業上ないし生活上の不利益を与えるのかなどの点を考慮して検討することになります。
ここで、業務命令の有効性に関して問題となった判例(最高裁昭和52年12月13日判決)をご紹介します。
この裁判は、会社から命じられた社内調査に協力しなかった従業員がけん責処分を受け、けん責処分は無効であるとして訴えを提起したものです。
けん責処分の前提として、そもそも従業員が会社の調査に協力する義務を負担するのか、社内調査に応じるようにとの業務命令が有効なものだったのかが争点となりました。
最高裁は、調査の対象となる従業員を指導、監督する立場にあるなど、他の従業員に対する調査に協力することがその従業員の職務内容となっている場合には、調査への協力は「労働契約上の基本的義務である労務提供義務の履行そのものであるから、右調査に協力すべき義務を負う」ものの、それ以外の場合については、調査対象である違反行為の性質、内容、当該労働者の違反行為見聞の機会と職務執行との関連性、より適切な調査方法の有無等諸般の事情から総合的に判断して、労働者が「調査に協力することが労務提供義務を履行する上で必要かつ合理的であると認められ」るときに限って調査に協力すべき義務を負うとしました。
その上で、この事案において従業員は調査協力義務を負っていなかったと判断し、そもそも社内調査に応じるようにとの業務命令は有効なものではないとしました。
そして、有効な業務命令でなかった以上、従業員がこれに応じなかったことを理由としてなされたけん責処分は無効と判断されています。 -
(2)懲戒処分の有効性
業務命令が有効であることを前提にして、命令に違反した従業員の懲戒処分について検討することになります。懲戒処分についても、業務命令と同様に、懲戒処分を行う根拠の確認をし、懲戒処分の行使が正当か(濫用になっていないか)を検討するというステップを踏みます。
- ① 懲戒処分を行う根拠
従業員に対して懲戒処分をするためには、就業規則に懲戒の種別(種類と程度)と事由を明確にした合理的な懲戒規定を設け、周知していることが必要です。 - ② 懲戒処分の行使が正当か(濫用になっていないか)
個々の懲戒処分の行使について有効性を検討するときには、業務命令に反した程度と懲戒処分の均衡・バランスが取れたものになっているかどうか、がポイントになります。
懲戒処分は労働契約法15条により、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない」場合には権利濫用として無効であることが定められています。
また、業務命令違反の内容にもよりますが、初めから重い処分を行ってしまうと、「社会通念上相当でない」として濫用と評価される可能性があります。たとえば、業務内容や仕事の順番などの日常的な業務にかかわる指揮命令に従わなかったからといって、反省や改善のための機会を与えることもなく、いきなり懲戒解雇処分をすることは、濫用と評価されてしまう可能性が高いでしょう。
そこで、まずは、口頭または書面による注意・指導を行い、それでも改善しなければ、けん責や減給などの比較的軽い懲戒処分を行って、その後も改善なく業務に支障が生じているという場合に懲戒解雇を検討するというように、段階的に処分の重さをあげていくことも有効です。
この点、最高裁平成24年4月27日判決は、従業員を諭して解雇を納得させ、通常の懲戒解雇よりも緩やかな条件で解雇する「諭旨解雇」という懲戒処分がなされた事案ですが、従業員がメンタルヘルス不調に伴い、事実として存在しない理由(自身への監視・嫌がらせ)によって約40日間欠勤したことを理由に、使用者が健康診断を受診させたり休職措置を講じたりすることなく諭旨解雇処分を行ったというものです。
この事案では、諭旨解雇処分は懲戒事由への該当性を欠くものとして無効と判断されました。
この判例のように、懲戒事由の存否や懲戒処分の選択により、懲戒処分が濫用にあたり無効と評価されてしまうリスクがあり、とりわけ懲戒解雇を行う場合には、慎重な対応が必要です。
解雇が無効となれば、従業員の会社への復職、未払賃金など多額の金銭の支払い、会社の信用の毀損といった問題が生じます。懲戒処分を検討する際には、このような問題の発生を避けるためにも、事前に弁護士へ相談するとよいでしょう。 - ① 懲戒処分を行う根拠
4、まとめ
指導や業務命令に従わない従業員に対して、どのように対応するべきなのか、懲戒処分を行うことはできるのか、皆さまからよく相談がありますが、懲戒処分が違法・無効と判断されてしまった裁判例は多数あり、慎重な対応が必要となります。
ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスでは、労務問題の実績が豊富な弁護士が対応いたします。問題ある従業員への対応についてお困りの際にはお気軽に当オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています